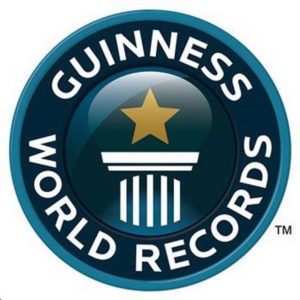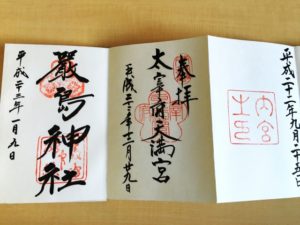本日は、宮大工についてお伝えしていきます。
学生時代アルバイトで大工の見習いをしていた時期がありますが、
そもそも向いていなかなかったのでしょう。
半年ほどで早々にリタイアしました。
そんなことはさておき、
早速ですが、
目次
スポンサードリンク
宮大工とは
主に神社や仏閣などの伝統建築を手掛ける職人を指します。
これは神社や仏閣を「お宮さん」と呼んでいたことに由来した呼称です
神社や仏閣は「木組み工法」で建てられているので、木組みの技術を習得している大工でなければなりません。参照 : [日本文化いろは辞典 『宮大工』項目]

宮大工の技術
この木組みの技術を習得するのが、とても大難しく、
一般の大工は2~3年の修行で一通りの仕事ができるようになりますが、
宮大工は一人前と呼ばれるまでに最低でも10年の修行が必要だということです。
木材の加工を全て手作業で行ったり、木の生育常態やそれぞれの木の性質を読み、
どういう用途に適すのかを判断したりなど、場数を踏んでいかないと身につかない芸当と言えるでしょう。
加工した木材を「継手」「仕口」と呼ばれる技術を用い、材と材を強固に繫ぎ合わせていくことで、
地震の多い日本の環境から建物を守ります。
パズルを組み合わせるような複雑な知識と共に、正確に材を削る技術が要求されます。
木材をはめ込み終えると、表面からは全くその複雑さは見えないばかりか、
繫ぎ目も殆ど分らないくらい精巧なものとなります。
宮大工の技術 「仕口」とは
2つ以上の材をある角度に接合する技術で、土台と柱のつなぎ目、梁と桁のつなぎ目などそれぞれの材を組むときに使われます。
宮大工の技術「継手」とは
木材の長さが足りない場合に、継ぎ足すときに使われる技術で、「腰掛鎌継ぎ」「台持ち継ぎ」「追掛け大栓継ぎ」など70くらいの種類があります。
このような宮大工の優れた技術は現在の建築工学から見ても非の打ち所のない技術だと言えるそうです。
実際の接木までにかかる工程が長い為、10年程は師匠の下で基礎を身体に叩き込む必要があります。
宮大工は各地の文化財を渡り歩き修理を行うので「渡り大工」とも呼ばれています。
現在では、その人数は100人もいないと言われています。
最低10年ってなかなか長さですよね。
仮に私が今から目指したら、40代で半人前になれているかどうかというところでしょうか。
きっと10年かけても木材を正確に削ることすらままならないと思いますが。。。
宮大工の歴史
最後に、宮大工の歴史をご紹介します。
宮大工の歴史は飛鳥時代に朝鮮から来た慧滋〔えじ〕と慧聡〔えそう〕という僧侶が飛鳥寺を建てた事に始まります。
これと同時期に聖徳太子も朝鮮から 来たこの二人の僧侶から教えを受け、法隆寺などに代表する歴史的建造物を建立したと言われています。
このように昔は僧侶が自身の寺社の建築や修理にたずさわり、宮大工の仕事をしているケースが多かったようです。参照 : [日本文化いろは辞典 『宮大工』項目]
僧侶と大工の両方の仕事をこなす事なんて、全然イメージできませんよね。
昔は屈強な僧侶が多かったりしたのでしょうか。
少し話がそれてしまいましたが、このように宮大工さんの持つ技術は、一朝一夕では習得する事の出来ないとても貴重な技術です。